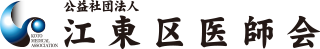区民公開講座 便秘は万病のもと?!今日からはじめる腸活のコツ
2024年11月30日(土) 15時00分~
江東区医師会館 4F 講堂
区民公開講座
便秘は万病のもと?!今日からはじめる腸活のコツ
河口内科眼科クリニック
院長 河口 貴昭
1.便秘は万病のもと
便は「腸からのお便り」、私たちに体の健康状態を教えてくれます。「便りのないのは良い便り」というわけにはいきません。便秘になるとおなかの張りや痛み、ガスなどのおなかの不調をきたすだけでなく、肌荒れやむくみ、気分不快などの原因にもなります。便には体にとって不要な老廃物や有害物質が含まれているので、腸内に長く溜めておいて健康に良いはずがありません。慢性の便秘症は、生活の質や労働生産性の低下、心筋梗塞や脳梗塞、パーキンソン病の発症リスクともなり、寿命に悪影響を与えると報告されています。便秘は万病のもとなのです。
2.便秘にはいくつかのタイプがある
便秘の症状は人によって様々で、その原因や対処法も人によって異なります。まずは自分の便秘のタイプを知ることが大切です。今回は4つの代表的な便秘の原因について解説します。
【つまり腸】
肛門から便をうまく排出できないタイプです(直腸性便秘)。肛門のすぐ奥で固く大きな便がたまっているため、排便時に強く息んだり、手でお腹を圧迫したり、浣腸や坐薬の力を借りたりしがちになります。排便後もすっきりしません(残便感)。高齢の方に多くみられ、便を排出するための筋力の低下や排便時に肛門が弛緩しにくいことなどが原因となります。若い方でも常時トイレを我慢していると直腸知覚が低下してこのタイプの便秘になることがあります。
【ねじれ腸】
大腸のねじれや下垂が原因で、腸の急カーブで便が停滞してしまうタイプです。腸が長い日本人に多いです。若い頃から便秘、いつも同じ所が痛くなる、便秘と下痢を繰り返しやすい、といった方はねじれ腸の可能性があります。ねじれ腸の方は運動不足、長時間のデスクワークや猫背などで姿勢が悪いと腸のねじれが解消されにくく、便秘しやすくなります。
【しまり腸】
大腸のけいれんが原因のタイプです(痙攣性便秘)。大腸のけいれんにより便が停滞し水分がどんどん吸収され、小さくコロコロとした硬い便になります。ストレスや生活リズムの乱れ、環境の変化などによる自律神経の乱れが原因となります。ストレスや旅行中に便秘になる方はしまり腸を疑います。
【ゆるみ腸】
大腸の動きが全体に低下しているため便が出ないタイプです(弛緩性便秘)。お腹が張っていても動いている感じはせず、便意をあまり感じません。主な原因はセンナ・大黄・アロエなどの成分が含まれる便秘薬(刺激性下剤)の長期服用です。刺激性下剤の使いすぎにより腸の神経が麻痺して動かなくなり便秘が悪化するという悪循環におちいります。刺激性下剤には頼らず、他のタイプの便秘薬に変更していきましょう。また加齢や神経系疾患、様々な薬の副作用でゆるみ腸になることがあります。
そのほかにも、大腸がんなど腸の重大な病気が原因で便秘になっていることもありますので、 ただの便秘と思わず、重大な病気が隠れていないか、一度は必ず大腸内視鏡検査でチェックしてください。
3.今日からはじめる腸活のコツ
腸のはたらきには「食事」「運動」「腸内フローラ」「自律神経」の4つの要素が重要です。
腸活を成功させるためにはこれら4要素を意識すると効果的です。
1)睡眠をしっかりとろう
自律神経のひとつである副交感神経は睡眠中に胃腸の働きを活性化させます。睡眠不足だと胃腸が働く時間がなくなり腸の「残業」を増やします。しっかり睡眠をとることは腸活にとってとても大切です。
2)朝食を摂ろう
胃に食べ物が入ると、その刺激で5〜30分後に大腸に大蠕動が生じ(胃-結腸反射)、大腸内の便が一気に直腸へと運ばれます。朝食を食べないと胃-結腸反射が起きず、朝の排便のチャンスを失うことになります。
3)食後は必ずトイレに行こう
生活リズムとして排便を習慣化することが大事です。また便意を感じたら我慢せずにトイレに行くことも大切。トイレではリラックスし、本やスマホを見るのはやめて便意に集中しましょう。和式トイレのしゃがみ込む姿勢は便を出すのに適しています。洋式トイレの方は足元に踏み台を置いて膝を高くし、両肘を太ももの上に乗せて前屈みになり、背筋を伸ばして腹筋に力を入れるとよいでしょう。
4)食物繊維と善玉菌を補おう
最近の日本人は食物繊維の摂取量が大きく不足していると言われています。食物繊維は玄米・雑穀米や野菜、豆類、果物などに多く含まれています。食物繊維は便の水分を保つ効果のほか、腸内の善玉菌のえさとしても重要です。食物繊維は善玉菌の発酵作用により酪酸などの短鎖脂肪酸に分解されますが、この短鎖脂肪酸が免疫の安定化やセロトニン産生を介した腸管蠕動亢進など様々な効果を発揮します。また善玉菌は腸内から悪玉菌を排除する役割もあります。善玉菌はヨーグルトや納豆など発酵食品から摂取することもできますが、腸内にいる善玉菌に良いえさ(様々な種類の食物繊維)を与えて腸内で増やしてあげることも大切です。なお当院では腸内フローラ検査(自費)を行っており、その方に適した腸活をサポートしています。
5)硬水を選ぼう
天然水にはミネラル分が少ない軟水とミネラル分が多く含まれる硬水があり、硬水に含まれるマグネシウムには便を柔らかくする作用があります。海外の天然水には硬水が多いで、外国産のミネラルウォーター(マグネシウムを多く含む製品)を選んで飲むと便秘に一定の効果があるでしょう。
6)体を動かそう
実は食物繊維を摂るだけでは便秘解消効果は少なく、便秘の解消には食物繊維(1日20g以上)に加えて水分摂取(1日2L)と有酸素運動(例:ウォーキングを週150分以上)を行うと効果的であるといわれています。運動には自律神経を整える効果や、便の移動、ねじれ腸の改善、腸の血行改善、ストレスの発散、排便に必要な筋力の向上など様々なメリットがあります。日頃から腹式呼吸で横隔膜を動かすことは腸を動かすのに効果的です。腹筋運動や体幹のひねり運動を行う際にも腹式呼吸を意識しましょう。「つまり腸」には仰向けでの腰上げ運動、「ねじれ腸」には腸もみマッサージ、「しまり腸」にはスポーツによるストレス発散、「ゆるみ腸」には「の」の字マッサージや腸の動きを刺激するツボ押し(天枢や合谷など)がおすすめです。おなかが冷えやすい方は入浴、腹巻き、運動、温かい飲み物 (しょうが湯など)を組み合わせると効果的ですし、山椒や生姜の成分が入った漢方「大建中湯」もおすすめです。
7)便秘薬は正しく使おう
以上の腸活に取り組んでも解消されない頑固な便秘の場合には便秘薬を使うことになります。便秘の治療薬は大きく分けて「便を軟らかくする」作用のものと「腸を刺激して動かす」作用のものがあります。「便を軟らかくする」薬の代表例は酸化マグネシウムで、長期に内服していても大丈夫です。「腸を刺激して動かす」薬は刺激性下剤といわれ、センナ・大黄・アロエといった成分が含まれる薬剤が該当します。腸を動かして便を押し出すので便秘解消効果は強いのですが、月〜年単位で毎日服用していると腸が刺激に対して麻痺してしまい、さらに腸が動かなくなるという悪循環(=ゆるみ腸)になってしまいます。
もし刺激性下剤が必要な場合には、どうしても便が出ないときの頓服薬として時々内服する程度にしましょう。
4.さいごに
便秘の原因や程度はひとによって様々です。日常生活の工夫で改善しない便秘については消化器専門医にご相談ください。